南田
2025/02/28 02:22
南田
2025/02/26 22:52
南田
2025/02/23 23:26
南田
2025/02/23 01:12
書きかけてて忘れてたオフに旅行しにいく雷真
そのうち気が向いたら続きを書きたいけどまた忘れそうなので途中まで置いておきます
疲れてるときに書いていたからテンションがいつもより低くてじわじわくる
紙カップのホットコーヒーを一口飲み、はあ、と息を吐く。
白い吐息が溶けて消えていくのを視線で追い、真田は何気なく新幹線のホームを見渡した。年末も差し迫った土曜の昼下がり、東京駅構内は観光客や帰省客のほか、スーツを纏ったビジネスマンたちでそこそこ混雑している。かくいう真田もつい昨日仕事を納めたばかりだった。休み中も自主練で球場には顔を出すつもりだが、今日からしばらくはゆっくりと羽を休めるつもりだ。
びゅう、と頬を刺すような冷たいからっ風がホームを吹き抜け、真田は思わず肩をすくめた。
お気に入りの黒いダウンコートは膝よりすこし上ほどの丈で、キルトステッチがないすっきりとしたデザインだ。左肩にかけた革製の黒いボストンバッグと合わせて、すらりと手足が長い真田のスタイルによく似合っている。その下にはハイネックのニットと保温性のあるインナーを着込んできたのだが、今日はひときわ風が冷たい。
「俊平さん!」
雑踏の中から聞き慣れた声が真田を呼んだ。
真田が顔をあげると人混みの向こうで手を振る雷市の姿が見える。
ぶんぶんと子どものように大きく動くものだから、すっかり目立ってしまっていた。真田は呆れ半分、愛おしさ半分で眉を下げて笑い、肩のあたりで小さく手を振り返した。
「おはよう、待たせてごめん」
駆け寄ってきた雷市が真田と同じ七号車の列に並ぶ。
急いで階段を駆け上がってきたのだろう、雷市は息を切らして、紅潮した顔をしている。
寒さで縮こまる真田と対照的に、暑いと言わんばかりにダウンジャケットの前立ちを開いた。
地元のテレビ番組の収録を終えた雷市は、その足で東京行きの新幹線に飛び乗ったとのことだった。もう何本か遅らせてよかったのに、早く俊平さんに会いたいから、なんて理由で全力疾走をしてくれる。何年経っても馬鹿みたいにまっすぐで可愛げのある男だった。ここが公共の場でなかったら、今すぐ抱きしめて立っていられないくらいのキスをお見舞いしてやったところだ。代わりに軽く頭を撫で、ぼさぼさになった髪を整えてやった。雷市は照れくさそうにはにかんで、されるがままだ。
「新幹線もまだ来てねぇし、ゆっくりでよかったのに。飲む?」
腕に提げていたコーヒーショップの紙袋からカップを差し出すと、雷市が嬉しそうに笑って受け取った。
ホットココアを飲む雷市は黒と鮮やかなグリーンのツートンカラーの大きめなダウンジャケットに、何年も愛用している黒のバックパックを背負っている。いずれも二人で買物をしたときに真田が雷市に勧めたものだった。こういう小さなことでも、未だにじわじわとこみあげるような喜びを感じてしまう。にやけそうな口元を隠すようにホットコーヒーを口に運びながら、横目で雷市を眺める。そんな真田の視線に雷市が気づいて、首を傾げた。
「どうしたの?」
「今日はバットとか持ってこなかったんだと思って」
ふ、と笑う。
「持ってくるつもりだったんだけど、向こうは雪降ってるって天気予報で言ってたから……さすがにやめとけって先輩が」
「あはは。軽く走るくらいにしといたほうがいいかもな」
「俊平さんも走る?」
「えぇ? うーん……そうだなぁ……なまっちゃいそうだけどなぁ……」
「走ろう! 服ある?」
「まぁ、あるけどさぁ……」
真田は苦笑いを浮かべた。
やる気のない素振りを見せたものの、ちゃんと運動用のウェアを持参していることを、雷市にはすっかり見透かされてしまっている。
雷市と他愛のない話をしているうちに、気づけば寒さは気にならなくなっていた。
程なくして到着した列車へ二人で一緒に乗りこんだ。雷市のバックパックと合わせて自分のボストンバッグを上の棚にしまい、二人席の通路側に座る。ダウンジャケットを脱いだ雷市は窓側の席に腰を下ろして、飲みかけのココアを背面テーブルに置いた。そしてじっと真田を見る。
「なに? 忘れ物したとか言うなよ」
冗談交じりに返すと、雷市は小さく頭を振る。
「すげー楽しみだなって思ってた」
そう告げて、にい、と白い歯を覗かせた。
真田は一瞬言葉につまったあと、目を細め、息を抜くように笑う。
「……俺も楽しみだよ」
真田の笑顔を見て、雷市の表情がより一層ぱあっと輝いた。
そうこうしているうちに新幹線が発車し、二人は東京を発った。目的地は――新潟県中央部にある湯沢町だ。東京駅から越後湯沢駅までは約一時間十分ほどの旅になる。次第に街並みが遠ざかっていく窓外の景色を――と見せかけて半分くらいは雷市の横顔を眺めながら、冷めきってしまったコーヒーを飲む。
待ちに待った、雷市との年末旅行だ。
しかも今回は初めての二泊三日の旅となる。
高校生の頃から付き合って六年目、気づけばこの時期の旅行が毎年の恒例行事になっていた。シーズン中の雷市は当然遠出などできるはずもなく、オフシーズンもなんだかんだと多忙の身だ。真田としては無理をしなくても、と思うのだが、雷市なりに思うところがあるのだろう。毎年こうして二人だけで過ごせる時間を設けてくれる。雷市は大人になっても相変わらず言葉足らずというか、口下手な男だったが、真田を不安にさせないようにと健気に考えてくれているんだろう。
好きだな、と、噛みしめるように実感しながら、窓の外に釘付けな雷市の横顔を眺めた。
「眠い? 寝ててもいいよ」
雷市は猫みたいに、すぐ真田の視線に気づいてしまう。
ばれてしまっては仕方ないと真田は笑って視線を外し、座席に背を預けた。
「やだよ。なんかもったいねーし」
雷市はわずかに目を見開いて、嬉しそうにへへ……と頬を緩める。
そうしてしばらくの間、二人は会話もなく、静かに窓の外を流れる景色を眺めていた。
遠くに連なる北関東の山々が徐々に近づいてくる。ずいぶんと都会を離れ、感じる非日常的な空気。旅行をしているのだと心が踊る――はずだった。少なくとも雷市はいま、まだ見ぬ未開の地に思いを馳せて少年のように胸を弾ませているだろう。
対する真田の胸中は、視線の先に広がる灰色の空のようにうっすらと重たい。
それは、一週間ほど前の出来事だった。
「あーーっはっはっは」
豪快な笑い声が居酒屋の個室から廊下まで響き渡る。
「ちょっと……岳さん笑いすぎだから」
赤ら顔をした真田は、凛々しい眉を不服そうに寄せる。
岳と呼ばれた男は畳の上でげらげらと笑い転げていた。すっかり出来上がっているようで、その顔は真田に負けず劣らず真っ赤でたこのようだ。大笑いする男をジト目で睨むこと一分ほど、やっと笑いの波が落ち着いたらしい男がゆっくりと大きな身体を起こす。がっしりとした身体つきをしたこの男は宮田岳といい、真田と同じ野球チームに所属する選手であり、チームの正捕手だ。真田とは入社当時からバッテリーを組んで早■年になる。高卒で入社した真田をよく気にかけてくれ、いまではプライベートな話も気兼ねなく打ち明けられる兄のような存在だった。
「予想外すぎてちょっと後逸したわ」
「俺のワイルドピッチだって?」
「いや、俺の捕球技術が足りんかった」
「岳さんなら真面目に聞いてくれるかなって思ったんすけど」
「悪い悪い。こんなとこに呼び出すからさぁ、来年あたり引退しますって話かと思うじゃん」
「まだやりますよ。少なくとも岳さんよりは長くね」
「言うね~」
人差し指を向けてウインクしてくる宮田をひと睨みすると、拗ねるなって、と諌められた。
「俊が恋人の話すんの珍しいな」
「……気の迷いっていうか。やっぱり言わなきゃよかったと思ってます」
「でも誰かに話したかったんだろ」
すっかりぬるくなったビールを飲み干して、まぁ、と言葉を濁した。
「まー、エッチする気満々だったのに向こうが途中で寝ちゃってたら凹むわなー」
「言わなくていいんで、そういうの!」
真田が真っ赤になって声を荒げると、あははと再び笑い声があがった。
真田の悩みというのは――端的に言えば、雷市との性行為に関する話であった。
高校生の頃から続く雷市との関係はもう■年目に突入し、東京と愛知という遠く離れた地で暮らしながらもうまくやっているとは思う。別れ話も幾度となく持ち上がったが、それでも結局お互いのいる人生がいいと思うに至るのだ。もうここまできたら一生傍から離れてやる気はないし、それは雷市だって同じなんだろう。一年を通して会えない時間のほうが長いけれど、忙しい中で会う機会を少しでも増やそうとしてくれる雷市の努力が嬉しいし、いじらしい。大事にされていると実感する。そんな雷市からの愛を疑う余地などない。しかし、そんな真田にもずっと気がかりなことがあった。
――セックスの回数が、あきらかに減っている。
昔は一晩で三、四回していたはずが、気づけば二回、少ないときは一回で終わる日も増えてきた。
お互い歳もとったし、仕方のない話だとは思う。雷市が一軍のレギュラーに定着した頃から多忙に拍車がかかったことも要因の一つだろう。夜遅くに待ち合わせをしてホテルに泊まり、始発で帰るなんて慌ただしいデートも少なくはない。
先々月のデートも同様の流れだったが、ついに雷市がセックスの途中で寝落ちてしまったのだ。ホテルに着いた段階でうとうととしていたから、予想通りといえばそうではあった。翌朝雷市は泣きそうな顔で平謝りしてくれたが、雷市を責めたいわけではなく、それでも完全にその気になってしまった己の身体を真夜中に一人しこしこと慰める虚しさは尾を引いて、ただ「気にすんなって」と頭を撫でてやることしかできなかった。
そんなことがあって迎えた先月のデートは真田が雷市の暮らす街へと赴く番だった。いくどとなく往復してきた愛知への道中、ずっとそわそわしていた。前回が不発に終わった分、とにかく雷市に激しく抱かれたかった。我慢できなくて、前日に自分で尻をいじりながら自慰をしてしまった。期待して、むらむらとして、どきどきしながらホテルに向かって、約二ヶ月ぶりのセックスはとろけそうなくらいに気持ちよくて――だが、その晩も結局一ラウンドで呆気なく終わってしまった。
がっかりした、とは思いたくなかった。セックス目当てで雷市に合っているわけではないのだし。顔を見られるだけでも嬉しいのだし。
――と自分に言い聞かせつつ、お前はこれで満足できてんのかよ、と悶々としたまま雷市の寝顔を眺めていたのが、つい先月の出来事であった。
「俺、性欲強すぎんのかなぁ、とか……思うわけで……」
テーブルにぐでんと突っ伏して、くだを巻く。
「いやまぁ……三十過ぎたら性欲減退なんて話よく聞くけどさぁ」
宮田は塩ゆでされた枝豆を太い親指で押し出して、ぱくりと食べる。
「筋肉多い人は性欲も衰えにくいんだってさ。なんだっけ……テスト……なんとかみたいな男性ホルモンが増えるから、みたいな。ほら、言うて俺らも一応アスリートでしょ。同年代の奴らより鍛え方が違うのよ。体力だってあるし」
宮田は太い自分の太ももをべしっと自慢げに叩いた。
なるほど、それは盲点だった。
しかし、それなら雷市だって同じでは? と思うものの、宮田には恋人が誰であるかは明かしていないので口に出すのは控えておく。
やっぱり、自分がムラムラしすぎなだけじゃないだろうか。
はぁー……と肩を落として、再びテーブルに臥せった。
「ほら、来週行くんだろ! 温泉!」
宮田の大きな手が、ゆさゆさと真田の肩を揺さぶってくる。
そう、来週には雷市との温泉旅行が迫っていた。
雷市が計画をたて、宿の予約までとってくれた。しかも二泊三日。浮かれないわけがないし、夜のあれそれを期待しないわけがない。――のだが、同時にそんなことばかり考えている自分がひどく不健全で、ただれた人間のように思えてならず、またもやもやとしてしまうのだった。
「温泉で思う存分いちゃいちゃすればいいじゃん」
「でも向こうがそういう気分じゃないかもしんねーし……」
「その気なかったら二泊で温泉行こうなんて言わねぇだろ」
「そうかぁ……」
「そうそう。そうだから。あ、若鶏の岩塩焼き頼んでもいい?」
むくりと起き上がるとすでに宮田はメニューを眺めて物色していた。
「話聞くの飽きてんじゃないすか」
「だってお前めんどいんだもん。高校時代からの付き合いなんだろ? もうそういうの遠慮せず話しちまえば?」
「それは、今まで培ってきた先輩としての威厳が……」
「一歳差! ねぇからそんなの!」
ぺしっとメニューで軽く額を叩かれた。
「俺だったらさみしいけどねー。信頼されてない感じがして」
さらりと告げられた宮田の何気ない一言に、どきりとした。
「俊平さん?」
はっと我に返る。
雷市が様子を伺うように、こちらを覗きこんでいた。
「大丈夫?」
「あ、ああ……うん。ごめん、ちょっと考えごとしてた」
雷市はまだ心配そうな顔をしているが、悩み事が悩み事なだけに居たたまれなくなる。
「そういや、ゴルフ行ってたよな」
そう言って、無理やり話題を変えた。
「楽しかった! 最下位だったけど!」
「お前ほんと野球に全振りしてるからなぁ……今年から旅行になったんだって?」
「うん、去年まで日帰りだったけど……今年はみんなで旅館に泊まって……あ、服もみんな褒めてくれた!」
雷市が誇らしげにぐっと親指を立てる。
毎年この時期のゴルフ納会に合わせ、真田がゴルフウェアを見立てていた。雷市いわく真田が選んでくれた服がひときわ評判いいのだという。そりゃ誰よりも一等この男の魅力を知っているのは俺ですから、なんて自負もあって、今年はとくに気合を入れて秋頃からいろんなブランドのウェアを物色していた。今年選んだのはグレーのダブルジップブルゾンで、フード部分にオレンジのラインが入っている。その下にオフホワイトのトレーナーとベージュのパンツ、黒いブランドロゴ入りのキャップを合わせて完璧なゴルフコーディネイトの完成だ。雷市のゴルフウェア姿はSNSでも「この二十七歳、可愛すぎる」と評判で、真田はその様子をにまにましながら眺めていた。当の本人も気に入ってくれたようで何よりだ。
「かっこよかったぜ、最下位だったけど」
「カハ……来年は優勝!」
「一気に飛びすぎだろ」
そんなとりとめのない話をしているうちに、新幹線は目的地である越後湯沢駅へと到着した。
駅を出るとすでに視界は真っ白で、あたり一面の雪景色が広がっていた。
ロータリーや道路の片隅に高く雪が高く積まれ、立ち並ぶ家々やその向こうに連なる大峯山も美しい雪化粧をまとっている。東京から一時間ほどしか離れていないというのに、まるで異国にでも来たようだ。
「すげー!」
雷市が子どものようにはしゃいでロータリーの屋根から飛び出し、忙しなく駅周辺を見渡していた。真田も足元に注意しながら、ゆっくりとその背中を追う。
「名古屋はまだ雪降ってねぇの」
「先週ちょっと降ったけど、積もるほどじゃなかった。東京もまだ?」
「うん。ちょっと早めに雪見られて、なんか得した気分」
雷市も嬉しそうにこくこく頷いた。
「でも寒いから早く店行こうぜ」
「うん!」
少し遅めの昼ご飯は駅近くにある蕎麦屋でとろうと、道中に決めていた。夕食までそう時間は空いていなかったが、なにせ二人とも元高校球児で、現役アスリートだ。食欲には自信がある。二人は迷うことなく蕎麦屋の暖簾をくぐった。食事どきからずれていたこともあり、店に入るなり待つことなく席に通された。
「へぎそば……普通のそばと違うのかな」
真田は雷市が手にしているメニューの裏側を覗いて、それをひっくり返す。
「ここに書いてあるぜ。そばを盛る木の器のことをへぎって言うんだってさ。ほら、あの横長いやつ」
「へー!」
「でもやっぱあったかいの食いたいよなー。俺、野菜天ぷらそばにしよ」
「んー……悩む……けど、普通の天ぷらうどん!」
「じゃ頼むか。すいませーん」
手を挙げて店員を呼び、手描きのメニューを指差しながら注文した。軽く頭を下げて去っていく男の店員を目で追い、そっとメニュー表を卓上スタンドに戻す。
「今の店員、雷市のこと気になってたな。野球好きなのかも」
「そう?」
「声かけられたらサインとかすんの?」
「時間があって、周りに迷惑かからなそうなら……移動中とかは無理だけど……なに?」
じい、と見つめる真田を不思議に思ったのか、雷市が首を傾げる。
「すっかり有名人だなーって思って」
「嫌なら、サングラスとかするようにするけど」
「違う違う。お前ってほんとすげーなって話」
真田は笑って手を左右に振った。
「でも、東京じゃなくてもお前のこと気付く人がいるなら……気ぃつけないとなー」
軽い口調でそう付け加えると、雷市はなにか言いたげな顔をした。
「おまたせしましたー天ぷらうどんと野菜天ぷらうどんです」
口を開きかけた雷市を遮るように、店員が蕎麦を運んでくる。
「ほら、冷めないうちに食おうぜ。いただきまーす」
真田が両手を合わせると、雷市もそれにならった。
二人の間に漂う微妙な空気は、熱々の蕎麦からたつ湯気と食欲をそそるつゆの匂い、そして蕎麦をすする音にかき消されていった。
予想通り、レジ対応をしてくれた先ほどの店員が雷市に向かって「頑張ってください」と遠慮がちに話しかけていた。畳む
そのうち気が向いたら続きを書きたいけどまた忘れそうなので途中まで置いておきます
疲れてるときに書いていたからテンションがいつもより低くてじわじわくる
紙カップのホットコーヒーを一口飲み、はあ、と息を吐く。
白い吐息が溶けて消えていくのを視線で追い、真田は何気なく新幹線のホームを見渡した。年末も差し迫った土曜の昼下がり、東京駅構内は観光客や帰省客のほか、スーツを纏ったビジネスマンたちでそこそこ混雑している。かくいう真田もつい昨日仕事を納めたばかりだった。休み中も自主練で球場には顔を出すつもりだが、今日からしばらくはゆっくりと羽を休めるつもりだ。
びゅう、と頬を刺すような冷たいからっ風がホームを吹き抜け、真田は思わず肩をすくめた。
お気に入りの黒いダウンコートは膝よりすこし上ほどの丈で、キルトステッチがないすっきりとしたデザインだ。左肩にかけた革製の黒いボストンバッグと合わせて、すらりと手足が長い真田のスタイルによく似合っている。その下にはハイネックのニットと保温性のあるインナーを着込んできたのだが、今日はひときわ風が冷たい。
「俊平さん!」
雑踏の中から聞き慣れた声が真田を呼んだ。
真田が顔をあげると人混みの向こうで手を振る雷市の姿が見える。
ぶんぶんと子どものように大きく動くものだから、すっかり目立ってしまっていた。真田は呆れ半分、愛おしさ半分で眉を下げて笑い、肩のあたりで小さく手を振り返した。
「おはよう、待たせてごめん」
駆け寄ってきた雷市が真田と同じ七号車の列に並ぶ。
急いで階段を駆け上がってきたのだろう、雷市は息を切らして、紅潮した顔をしている。
寒さで縮こまる真田と対照的に、暑いと言わんばかりにダウンジャケットの前立ちを開いた。
地元のテレビ番組の収録を終えた雷市は、その足で東京行きの新幹線に飛び乗ったとのことだった。もう何本か遅らせてよかったのに、早く俊平さんに会いたいから、なんて理由で全力疾走をしてくれる。何年経っても馬鹿みたいにまっすぐで可愛げのある男だった。ここが公共の場でなかったら、今すぐ抱きしめて立っていられないくらいのキスをお見舞いしてやったところだ。代わりに軽く頭を撫で、ぼさぼさになった髪を整えてやった。雷市は照れくさそうにはにかんで、されるがままだ。
「新幹線もまだ来てねぇし、ゆっくりでよかったのに。飲む?」
腕に提げていたコーヒーショップの紙袋からカップを差し出すと、雷市が嬉しそうに笑って受け取った。
ホットココアを飲む雷市は黒と鮮やかなグリーンのツートンカラーの大きめなダウンジャケットに、何年も愛用している黒のバックパックを背負っている。いずれも二人で買物をしたときに真田が雷市に勧めたものだった。こういう小さなことでも、未だにじわじわとこみあげるような喜びを感じてしまう。にやけそうな口元を隠すようにホットコーヒーを口に運びながら、横目で雷市を眺める。そんな真田の視線に雷市が気づいて、首を傾げた。
「どうしたの?」
「今日はバットとか持ってこなかったんだと思って」
ふ、と笑う。
「持ってくるつもりだったんだけど、向こうは雪降ってるって天気予報で言ってたから……さすがにやめとけって先輩が」
「あはは。軽く走るくらいにしといたほうがいいかもな」
「俊平さんも走る?」
「えぇ? うーん……そうだなぁ……なまっちゃいそうだけどなぁ……」
「走ろう! 服ある?」
「まぁ、あるけどさぁ……」
真田は苦笑いを浮かべた。
やる気のない素振りを見せたものの、ちゃんと運動用のウェアを持参していることを、雷市にはすっかり見透かされてしまっている。
雷市と他愛のない話をしているうちに、気づけば寒さは気にならなくなっていた。
程なくして到着した列車へ二人で一緒に乗りこんだ。雷市のバックパックと合わせて自分のボストンバッグを上の棚にしまい、二人席の通路側に座る。ダウンジャケットを脱いだ雷市は窓側の席に腰を下ろして、飲みかけのココアを背面テーブルに置いた。そしてじっと真田を見る。
「なに? 忘れ物したとか言うなよ」
冗談交じりに返すと、雷市は小さく頭を振る。
「すげー楽しみだなって思ってた」
そう告げて、にい、と白い歯を覗かせた。
真田は一瞬言葉につまったあと、目を細め、息を抜くように笑う。
「……俺も楽しみだよ」
真田の笑顔を見て、雷市の表情がより一層ぱあっと輝いた。
そうこうしているうちに新幹線が発車し、二人は東京を発った。目的地は――新潟県中央部にある湯沢町だ。東京駅から越後湯沢駅までは約一時間十分ほどの旅になる。次第に街並みが遠ざかっていく窓外の景色を――と見せかけて半分くらいは雷市の横顔を眺めながら、冷めきってしまったコーヒーを飲む。
待ちに待った、雷市との年末旅行だ。
しかも今回は初めての二泊三日の旅となる。
高校生の頃から付き合って六年目、気づけばこの時期の旅行が毎年の恒例行事になっていた。シーズン中の雷市は当然遠出などできるはずもなく、オフシーズンもなんだかんだと多忙の身だ。真田としては無理をしなくても、と思うのだが、雷市なりに思うところがあるのだろう。毎年こうして二人だけで過ごせる時間を設けてくれる。雷市は大人になっても相変わらず言葉足らずというか、口下手な男だったが、真田を不安にさせないようにと健気に考えてくれているんだろう。
好きだな、と、噛みしめるように実感しながら、窓の外に釘付けな雷市の横顔を眺めた。
「眠い? 寝ててもいいよ」
雷市は猫みたいに、すぐ真田の視線に気づいてしまう。
ばれてしまっては仕方ないと真田は笑って視線を外し、座席に背を預けた。
「やだよ。なんかもったいねーし」
雷市はわずかに目を見開いて、嬉しそうにへへ……と頬を緩める。
そうしてしばらくの間、二人は会話もなく、静かに窓の外を流れる景色を眺めていた。
遠くに連なる北関東の山々が徐々に近づいてくる。ずいぶんと都会を離れ、感じる非日常的な空気。旅行をしているのだと心が踊る――はずだった。少なくとも雷市はいま、まだ見ぬ未開の地に思いを馳せて少年のように胸を弾ませているだろう。
対する真田の胸中は、視線の先に広がる灰色の空のようにうっすらと重たい。
それは、一週間ほど前の出来事だった。
「あーーっはっはっは」
豪快な笑い声が居酒屋の個室から廊下まで響き渡る。
「ちょっと……岳さん笑いすぎだから」
赤ら顔をした真田は、凛々しい眉を不服そうに寄せる。
岳と呼ばれた男は畳の上でげらげらと笑い転げていた。すっかり出来上がっているようで、その顔は真田に負けず劣らず真っ赤でたこのようだ。大笑いする男をジト目で睨むこと一分ほど、やっと笑いの波が落ち着いたらしい男がゆっくりと大きな身体を起こす。がっしりとした身体つきをしたこの男は宮田岳といい、真田と同じ野球チームに所属する選手であり、チームの正捕手だ。真田とは入社当時からバッテリーを組んで早■年になる。高卒で入社した真田をよく気にかけてくれ、いまではプライベートな話も気兼ねなく打ち明けられる兄のような存在だった。
「予想外すぎてちょっと後逸したわ」
「俺のワイルドピッチだって?」
「いや、俺の捕球技術が足りんかった」
「岳さんなら真面目に聞いてくれるかなって思ったんすけど」
「悪い悪い。こんなとこに呼び出すからさぁ、来年あたり引退しますって話かと思うじゃん」
「まだやりますよ。少なくとも岳さんよりは長くね」
「言うね~」
人差し指を向けてウインクしてくる宮田をひと睨みすると、拗ねるなって、と諌められた。
「俊が恋人の話すんの珍しいな」
「……気の迷いっていうか。やっぱり言わなきゃよかったと思ってます」
「でも誰かに話したかったんだろ」
すっかりぬるくなったビールを飲み干して、まぁ、と言葉を濁した。
「まー、エッチする気満々だったのに向こうが途中で寝ちゃってたら凹むわなー」
「言わなくていいんで、そういうの!」
真田が真っ赤になって声を荒げると、あははと再び笑い声があがった。
真田の悩みというのは――端的に言えば、雷市との性行為に関する話であった。
高校生の頃から続く雷市との関係はもう■年目に突入し、東京と愛知という遠く離れた地で暮らしながらもうまくやっているとは思う。別れ話も幾度となく持ち上がったが、それでも結局お互いのいる人生がいいと思うに至るのだ。もうここまできたら一生傍から離れてやる気はないし、それは雷市だって同じなんだろう。一年を通して会えない時間のほうが長いけれど、忙しい中で会う機会を少しでも増やそうとしてくれる雷市の努力が嬉しいし、いじらしい。大事にされていると実感する。そんな雷市からの愛を疑う余地などない。しかし、そんな真田にもずっと気がかりなことがあった。
――セックスの回数が、あきらかに減っている。
昔は一晩で三、四回していたはずが、気づけば二回、少ないときは一回で終わる日も増えてきた。
お互い歳もとったし、仕方のない話だとは思う。雷市が一軍のレギュラーに定着した頃から多忙に拍車がかかったことも要因の一つだろう。夜遅くに待ち合わせをしてホテルに泊まり、始発で帰るなんて慌ただしいデートも少なくはない。
先々月のデートも同様の流れだったが、ついに雷市がセックスの途中で寝落ちてしまったのだ。ホテルに着いた段階でうとうととしていたから、予想通りといえばそうではあった。翌朝雷市は泣きそうな顔で平謝りしてくれたが、雷市を責めたいわけではなく、それでも完全にその気になってしまった己の身体を真夜中に一人しこしこと慰める虚しさは尾を引いて、ただ「気にすんなって」と頭を撫でてやることしかできなかった。
そんなことがあって迎えた先月のデートは真田が雷市の暮らす街へと赴く番だった。いくどとなく往復してきた愛知への道中、ずっとそわそわしていた。前回が不発に終わった分、とにかく雷市に激しく抱かれたかった。我慢できなくて、前日に自分で尻をいじりながら自慰をしてしまった。期待して、むらむらとして、どきどきしながらホテルに向かって、約二ヶ月ぶりのセックスはとろけそうなくらいに気持ちよくて――だが、その晩も結局一ラウンドで呆気なく終わってしまった。
がっかりした、とは思いたくなかった。セックス目当てで雷市に合っているわけではないのだし。顔を見られるだけでも嬉しいのだし。
――と自分に言い聞かせつつ、お前はこれで満足できてんのかよ、と悶々としたまま雷市の寝顔を眺めていたのが、つい先月の出来事であった。
「俺、性欲強すぎんのかなぁ、とか……思うわけで……」
テーブルにぐでんと突っ伏して、くだを巻く。
「いやまぁ……三十過ぎたら性欲減退なんて話よく聞くけどさぁ」
宮田は塩ゆでされた枝豆を太い親指で押し出して、ぱくりと食べる。
「筋肉多い人は性欲も衰えにくいんだってさ。なんだっけ……テスト……なんとかみたいな男性ホルモンが増えるから、みたいな。ほら、言うて俺らも一応アスリートでしょ。同年代の奴らより鍛え方が違うのよ。体力だってあるし」
宮田は太い自分の太ももをべしっと自慢げに叩いた。
なるほど、それは盲点だった。
しかし、それなら雷市だって同じでは? と思うものの、宮田には恋人が誰であるかは明かしていないので口に出すのは控えておく。
やっぱり、自分がムラムラしすぎなだけじゃないだろうか。
はぁー……と肩を落として、再びテーブルに臥せった。
「ほら、来週行くんだろ! 温泉!」
宮田の大きな手が、ゆさゆさと真田の肩を揺さぶってくる。
そう、来週には雷市との温泉旅行が迫っていた。
雷市が計画をたて、宿の予約までとってくれた。しかも二泊三日。浮かれないわけがないし、夜のあれそれを期待しないわけがない。――のだが、同時にそんなことばかり考えている自分がひどく不健全で、ただれた人間のように思えてならず、またもやもやとしてしまうのだった。
「温泉で思う存分いちゃいちゃすればいいじゃん」
「でも向こうがそういう気分じゃないかもしんねーし……」
「その気なかったら二泊で温泉行こうなんて言わねぇだろ」
「そうかぁ……」
「そうそう。そうだから。あ、若鶏の岩塩焼き頼んでもいい?」
むくりと起き上がるとすでに宮田はメニューを眺めて物色していた。
「話聞くの飽きてんじゃないすか」
「だってお前めんどいんだもん。高校時代からの付き合いなんだろ? もうそういうの遠慮せず話しちまえば?」
「それは、今まで培ってきた先輩としての威厳が……」
「一歳差! ねぇからそんなの!」
ぺしっとメニューで軽く額を叩かれた。
「俺だったらさみしいけどねー。信頼されてない感じがして」
さらりと告げられた宮田の何気ない一言に、どきりとした。
「俊平さん?」
はっと我に返る。
雷市が様子を伺うように、こちらを覗きこんでいた。
「大丈夫?」
「あ、ああ……うん。ごめん、ちょっと考えごとしてた」
雷市はまだ心配そうな顔をしているが、悩み事が悩み事なだけに居たたまれなくなる。
「そういや、ゴルフ行ってたよな」
そう言って、無理やり話題を変えた。
「楽しかった! 最下位だったけど!」
「お前ほんと野球に全振りしてるからなぁ……今年から旅行になったんだって?」
「うん、去年まで日帰りだったけど……今年はみんなで旅館に泊まって……あ、服もみんな褒めてくれた!」
雷市が誇らしげにぐっと親指を立てる。
毎年この時期のゴルフ納会に合わせ、真田がゴルフウェアを見立てていた。雷市いわく真田が選んでくれた服がひときわ評判いいのだという。そりゃ誰よりも一等この男の魅力を知っているのは俺ですから、なんて自負もあって、今年はとくに気合を入れて秋頃からいろんなブランドのウェアを物色していた。今年選んだのはグレーのダブルジップブルゾンで、フード部分にオレンジのラインが入っている。その下にオフホワイトのトレーナーとベージュのパンツ、黒いブランドロゴ入りのキャップを合わせて完璧なゴルフコーディネイトの完成だ。雷市のゴルフウェア姿はSNSでも「この二十七歳、可愛すぎる」と評判で、真田はその様子をにまにましながら眺めていた。当の本人も気に入ってくれたようで何よりだ。
「かっこよかったぜ、最下位だったけど」
「カハ……来年は優勝!」
「一気に飛びすぎだろ」
そんなとりとめのない話をしているうちに、新幹線は目的地である越後湯沢駅へと到着した。
駅を出るとすでに視界は真っ白で、あたり一面の雪景色が広がっていた。
ロータリーや道路の片隅に高く雪が高く積まれ、立ち並ぶ家々やその向こうに連なる大峯山も美しい雪化粧をまとっている。東京から一時間ほどしか離れていないというのに、まるで異国にでも来たようだ。
「すげー!」
雷市が子どものようにはしゃいでロータリーの屋根から飛び出し、忙しなく駅周辺を見渡していた。真田も足元に注意しながら、ゆっくりとその背中を追う。
「名古屋はまだ雪降ってねぇの」
「先週ちょっと降ったけど、積もるほどじゃなかった。東京もまだ?」
「うん。ちょっと早めに雪見られて、なんか得した気分」
雷市も嬉しそうにこくこく頷いた。
「でも寒いから早く店行こうぜ」
「うん!」
少し遅めの昼ご飯は駅近くにある蕎麦屋でとろうと、道中に決めていた。夕食までそう時間は空いていなかったが、なにせ二人とも元高校球児で、現役アスリートだ。食欲には自信がある。二人は迷うことなく蕎麦屋の暖簾をくぐった。食事どきからずれていたこともあり、店に入るなり待つことなく席に通された。
「へぎそば……普通のそばと違うのかな」
真田は雷市が手にしているメニューの裏側を覗いて、それをひっくり返す。
「ここに書いてあるぜ。そばを盛る木の器のことをへぎって言うんだってさ。ほら、あの横長いやつ」
「へー!」
「でもやっぱあったかいの食いたいよなー。俺、野菜天ぷらそばにしよ」
「んー……悩む……けど、普通の天ぷらうどん!」
「じゃ頼むか。すいませーん」
手を挙げて店員を呼び、手描きのメニューを指差しながら注文した。軽く頭を下げて去っていく男の店員を目で追い、そっとメニュー表を卓上スタンドに戻す。
「今の店員、雷市のこと気になってたな。野球好きなのかも」
「そう?」
「声かけられたらサインとかすんの?」
「時間があって、周りに迷惑かからなそうなら……移動中とかは無理だけど……なに?」
じい、と見つめる真田を不思議に思ったのか、雷市が首を傾げる。
「すっかり有名人だなーって思って」
「嫌なら、サングラスとかするようにするけど」
「違う違う。お前ってほんとすげーなって話」
真田は笑って手を左右に振った。
「でも、東京じゃなくてもお前のこと気付く人がいるなら……気ぃつけないとなー」
軽い口調でそう付け加えると、雷市はなにか言いたげな顔をした。
「おまたせしましたー天ぷらうどんと野菜天ぷらうどんです」
口を開きかけた雷市を遮るように、店員が蕎麦を運んでくる。
「ほら、冷めないうちに食おうぜ。いただきまーす」
真田が両手を合わせると、雷市もそれにならった。
二人の間に漂う微妙な空気は、熱々の蕎麦からたつ湯気と食欲をそそるつゆの匂い、そして蕎麦をすする音にかき消されていった。
予想通り、レジ対応をしてくれた先ほどの店員が雷市に向かって「頑張ってください」と遠慮がちに話しかけていた。畳む
南田
2025/02/16 08:59
南田
2025/02/16 08:59
南田
2025/02/6 17:57










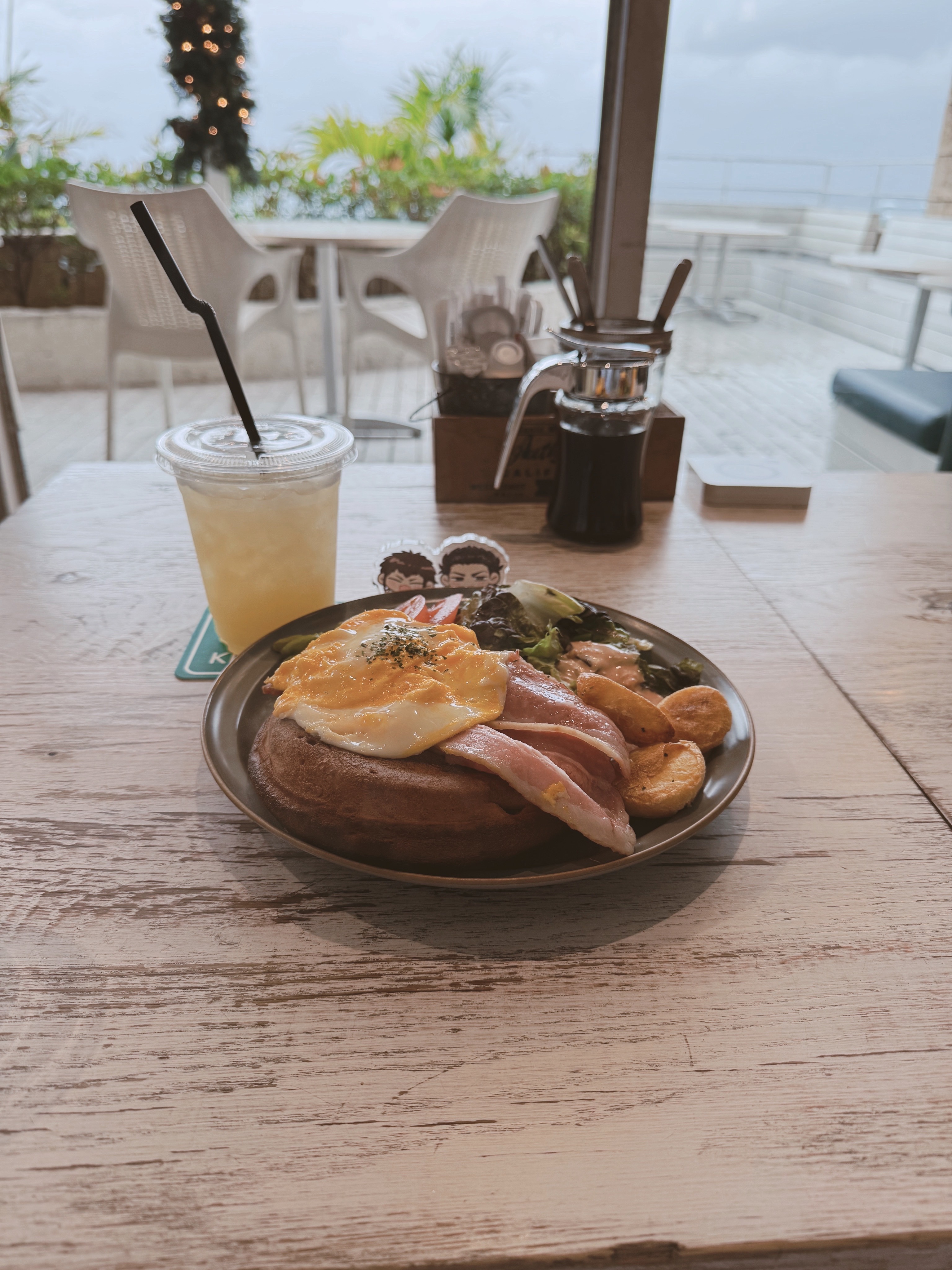


https://wavebox.me/msg/e66f336x5dhrim4t/...