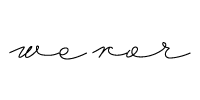今さら好きって言えるかよ (5)
「十三段の……もう少しこっちかな」
真田はチケットを片手に周囲を見渡した。
今日もドームはほぼ満員だ。立ち見も完売することあるから早めにチケット確保しておけよ、と助言してくれた平畠に感謝をしながら、混みあう客席を進んでいく。なんとかたどり着いた座席に腰を下ろし、一息ついた。
「……思ったより近いな」
平畠に薦められるままグラウンドに近い内野席をとったはいいものの、想像以上に選手たちがよく見える。なんだか緊張してしまい、そわそわとしながらビールを飲んでいるうちに試合が始まった。
遠征先で負け越し、迎えたホームゲームだ。勝利を望むファンの熱気がぶわりと大きく膨れあがって、ドームを包みこむようだった。両チーム無失点、緊迫感のある投手戦でゲームが進んでいく。
懐かしいアニメのオープニング曲とともに、二死走者一塁二塁で雷市に打順が回ってきた。
これは秋葉経由で平畠から聞いた話だったが、雷市が登場曲を決めかねていたところ、高校時代の応援歌がアニソンだったことからチームの先輩が「お前アニメのキャラっぽいし、アニメの曲にしようぜ」と提案してくれたらしい。確かに、派手で力強いメロディが雷市によく似合っている。
最強というフレーズが入っているのもいい。
周囲の観客の手拍子にあわせて真田も自然とノってしまった。
雷市が軽くバットを振り、打席に立つ。
応援団の演奏にあわせて雷市の応援歌がドーム全体に響きわたった。ビリビリと空気が震えるような、とてつもない熱量だ。あっという間にツーストライクまで追いこまれた雷市だったが、そこから粘り、よく見て、フルカウントを迎えた。雷市の一発を渇望する観客たちの声援が、より一層激しさを増していく。
そして、力強く振り抜いた雷市のバットは外角に入ったストレートを捕らえて――センターの手前に落ちた。
瞬間、割れんばかりの歓声が沸きおこる。
気づけば真田も大声をあげて雷市の名前を叫んでいた。全力疾走で一塁を踏んだ雷市が、雄叫びをあげながら元気いっぱいに拳を突き上げる。試合の流れを一気に変える、見事な勝ち越しタイムリーツーベスヒットだった。
「っ……あは……あいつ……」
高校の頃から変わらない姿に、思わず笑いがこぼれた。
心臓がばくばくしている。
興奮で手が震える。
顔が、熱い。
もちろん、その日のお立ち台に立ったのは雷市だった。
会社の寮に帰ってからも、身体の奥が熱を持っているようだった。
シャワーを浴びて、ベッドにごろんと横になる。SNSで雷市の名前を検索すると、ファンが撮影した雷市の写真や動画であふれかえっていた。
球団公式アカウントが「本日のヒーローはもちろんこの人!」という文章とともにアップしていたのは、無邪気に笑う雷市の写真だ。顔つきもずいぶん大人びたとはいえ、笑い方は昔とちっとも変わっていない。あの頃の雷市のままだった。たまらなくかわいい、と思う。
「……マジでヒーローじゃん」
心臓が、きゅう、となる。
雷市への恋心を自覚してからというのも、自分がどれだけ雷市のことを好きだったのかを日々痛感している。というか、これだけ骨抜きになっておきながら全く気づいていなかったことが信じがたい。
雷市に会いたかった。
でも今さら会ってどうするんだよ、と思う自分もいる。 雷市とは連作先を交換してあるが、プロ入りが決まったときにお祝いのメッセージを送ったきりだ。
長らく使われていない雷市とのトーク画面を開いたまま、真田はぐるぐると考えこんだ。
それなりに仲がよかったとは思うけど、いきなり連絡するのも変かな、とか。雷市だって忙しいだろうし、そう簡単に会う約束取りつけらんねーよな、とか。
そんなことを考えているうちに次第と眠くなってくる。うとうととしかけた矢先、オフになっていた画面がぱっと明るく点灯した。誰かからの着信だ。
通知画面に表示されていたのは、雷市の名前だった。
「……えっ!?」
一気に目が覚めて、がばっと起き上がる。
雷市から電話?
なんで?
夢?
わけがわからないまま、慌てて電話に出た。
「も、もしもし?」
「……あっ。真田、先輩ですか?」
電話越しに聞こえたのは、間違いなく雷市の声だった。
うわ、雷市だ。
そう実感した途端、一気に緊張が高まった。
「うん、俺……だけど。どうした?」
平然を取りつくろおうとするが、どうしたって声が上ずる。音をたてないようにつばを飲みこんだ。
「試合……その、観に来てくれてる、って平畠先輩から聞いて……」
あいつ……と、喉元まで出かかった声をぐっと飲みこんだ。
「ありがとう。すげー、嬉しい……です。って、伝えたくて……ごめんなさい。急に」
「いや、びっくりしたけど……大丈夫」
そこで会話が途切れてしまった。
気まずい沈黙が流れる。
大丈夫ってなんだよ、バカ。もっと気の利いた返しあっただろ。どうしよう。なんとかしないと、雷市のことだからすぐに電話を切りかねない。この機会を逃したら、雷市ともう会えないような気がした。
「あ、あのさ。今度メシでも行かない?」
電話の向こうで、雷市が小さく息を呑んだのがわかる。さすがに急すぎただろうか。
「いや、雷市も忙しいだろうし、今すぐって話じゃないんだけどさ」
「行く!」
雷市が食い気味に声をあげた。
「真田先輩、次の休みっていつ?」
まさかそんな展開になるとは思っておらず、真田はおおいに慌てふためいた。
「え? えっと……うわっ」
動揺しながらテーブルの上に置いた手帳を手にとると、隣に積んでいた参考書がどさどさと床に崩れおちた。
「うんめぇー……」
焼き鳥を頬張り、雷市が感嘆の息をもらす。
こうして雷市と顔を合わせるのは真田の卒業式以来のことだった。久々の再会に緊張していたが、少し遅れて店に現れた雷市はあの頃のままで、真田は少しほっとした。体つきこそがっしりと男らしさを増しているものの、笑う仕草だとか、雰囲気はまったく変わっていない。
四年近く会っていなかったのが嘘みたいに、二人はごく自然に話ができた。まるで高校生の頃に戻ったようだった。
「それなに?」
「なんか味噌の味……えっと、ごま味噌? だって」
「ふーん……あ、うまいな」
カハハ、と雷市が嬉しそうに笑った。
悩みに悩んで選んだ串料理の店だったが、喜んでもらえたようで何よりだ。ただ、個室が思っていたよりも狭く、雷市との距離が近いのが想定外だった。
個室に通されてからというもの、真田はずっとドキドキとしている。バレてなきゃいいけど、と思いながら、鶏皮が盛りつけられた皿を雷市の前に寄せた。
「ほら、もっと食えよ。これが一番人気なんだってさ」
「先輩も食ってる?」
「食ってる食ってる」
真田が串にささった鶏皮を口に運ぶと、雷市も同じ皿から串を一本手に取った。
「ん、んま」
「んめー!」
看板メニューらしい炙りの鶏皮は味付けも濃く、ビールが進みそうだ。
追加でビール頼んでおいたほうがいいかな、と雷市に視線を向ける。同じことを考えていたらしい雷市と目があった。真田が話を切りだすより早く、雷市が「生でいい?」と聞いてきた。
「あ、うん」
「わかった。他に追加でなにか頼む?」
「そうだなぁ……」
メニューを開きながら、真田はずいぶん慣れた様子の雷市に少しだけ動揺していた。
――そりゃそうだよな。付き合いだって多いだろうし、飲みの席だって慣れるよなあ。
そう言い聞かせてみるが、自分の中の雷市が「高校生の雷市」のままで止まっていたことを思い知らされて、メニュー表の文字列が頭に入ってこない。
「先輩? 大丈夫?」
訝しそうに雷市が声をかけてきて、我に返った。
「あ、ああ。悪い……雷市まだ食えるよな」
「うん」
「じゃ、このへんと……釜飯食う?」
雷市はこくんと頷いて、店員を呼んだ。メニューを指さして追加注文をする雷市の姿を眺め、なんだか雷市がとても遠い存在になってしまったような感覚を味わった。スーパーの店員に話しかけられただけであたふたと挙動をおかしくしていた昔の雷市を思い出し、ふ、と笑いがもれる。
「なんかおかしいこと……あった?」
店員が部屋を出ていき、雷市が不思議そうに首を傾げる。こういうちょっとした仕草は、高校のときの雷市と変わらない。部活中、らいちーと呼ぶと首を傾げながら駆けよってくるのがなんだか可愛いくて、猫みたいだなと感じていたことを思い出す。
「なんでも。そういや、平畠と試合観に行ったときの話なんだけど……あのサヨナラは痺れたわ」
急な話題転換にきょとんとしながらも、雷市は照れたようにはにかんだ。
「うん。前のカードは俺のエラーで失点して負けちゃったから……勝ててよかった」
「また見たいな、お前のさよならタイムリー」
「カハ……今度来てくれたとき、打つ!」
「お前が言うとほんとにやってくれそうなんだよな~」
カハハ! と屈託のない笑い声が心地よくて、もっと聞いていたくなって、胸が苦しい。
好きだな、と思い知らされる。
――なぁ、雷市。
あの日泣いてたお前の顔、今でも思い出すんだよ。
ばかみたいだよな。今さら好きだって気づいてさ。すげー好きで、好きで、お前の笑顔見ただけで胸が苦しくなってさ。あのときお前の告白を受けてたら、今でも俺らって付きあってたのかなとか考えてさ。遅すぎるよな。
だなんて、言えるわけもない想いをビールと一緒にぐいぐいと胃の奥に流しこんだ。
追加で届いた釜飯をうまいうまいと言い合って食べている最中も、店を出て駅に向かう道中も、ずっとずっと、真田は喉まで出かかった言葉を何度も飲みこんだ。
――俺、お前のこと好きなんだ。
そう言ったら雷市はどんな顔をするんだろう。
真田の胸中なんて雷市には知るよしもなく、結局あの日のことを口にすら出来ないまま、駅前で笑って雷市と別れた。
「あ、しゅんしゅんー」
午前中のトレーニングを終え、食堂へ向かう途中で後ろから呼びとめられた。振り向くと背後からがしっと肩を組まれる。
「なんすか」
三つ上の先輩は内野手で、真田の制球が乱れるとすぐにマウンドまで声をかけてくれる気さくな男だった。マウンドでするように手元で口元を隠して、声をひそめながら
「お前の後輩……轟、すっぱぬかれてんぞ」
と、神妙な面持ちで切りだしてくる。
「は?」
「これ」
差し出された先輩のスマートフォンを手にとり、ブラウザで開かれたままになっているニュースサイトに目を通す。
先輩の言うとおり、その記事では雷市と女性シンガーソングライターとの熱愛報道が取り上げられていた。
幼少期から球団のファンであった彼女は始球式にも登板しており、自身のラジオ番組で雷市の活躍についてたびたび言及していたという。
遠目ではあるが、雷市と彼女らしき女性が飲食店から出てきたときの写真も掲載されている。雷市であると断言できないほどひどくブレた写真ではあったが、真田はここに映っている男が雷市だと一目見て確信してしまった。なぜなら、この前会ったときとまったく同じ服装をしていたからだ。
少しだぼっとしたシルエットのパーカーに、膝丈のタックパンツ。見覚えがありすぎた。ネットでの反応を見てみると、真田と同様に「この服着てるの見たことあるから雷市くんじゃないの?」と指摘しているファンも複数いて、真田は思わず額を抑えた。
雷市は昔からファッションに疎いというか、まったく興味のない男ではあった。こんなところでスキャンダルに信憑性が出てくるあたり、雷市らしいと言えば雷市らしい。
――なんだ。彼女いたんじゃん。
悲しみや落胆といった感情よりも先に、「そりゃそうだよな」と納得している自分がいた。
あれからもう二年以上経ってるし、雷市だって恋人ぐらいいるよな。プロの野球選手なんだし。
モテるのも当然の話だった。
なにを期待したんだろう、俺は。
真田は自嘲気味に小さく笑って、先輩にスマートフォンを返した。
「こういうとこ甘いんすよねー、こいつ」
「全然女っけなさそうなのにな」
「言うて男ですからね。俺より早く結婚するかも」
「俊はまず彼女つくるとこからな」
「あはは。そんな暇あるかなー」
他愛のない会話をしながら食べたその日の昼食がなんだったのか、真田はさっぱり覚えていなかった。
雷市のスキャンダルが報じられてから一晩経った。今日はちょうど月曜日だから試合もない。翌日の試合までに球団からなにかしらの説明があるかも、なんてファンたちは噂していた。
どうあっても、真田には関係のない話だった。
真田は雷市にとって「高校時代の先輩」でしかない。マスコミへの対応で練習やプレーに支障が出なければいいけど、という危惧はあるものの、だからといって真田が雷市のためにできることなんて一つもない。
こんなときに「大丈夫か?」なんて連絡するのも野暮だし、迷惑な話だろう。
というわけで、真田は今日も練習に精を出している。
構えられた正面のミットに向かって、球を投げる。
パァン、と小気味よい音がブルペンに響いた。
もう一球、と真田が構えた矢先、投球練習に付きあってくれていた捕手が、突然片手を挙げて立ち上がる。
真田が上げかけた足を地面に戻すと、捕手である先輩がカシャカシャと音をたてながら駆けよってくる。
「なんか問題でもありました?」
彼はマスクを外し、真田の顔をじっと見つめた。
チームの正捕手であるこの男は真田より五つ年上で、面倒見の良さからみんなの兄貴分のような存在だった。バッテリーを組む機会が多いこともあって、真田もこの捕手のことをよく慕っていた。
「俊平、なんかあったのか」
「え? なんもないですけど」
内心ぎくっとしながらも、笑って誤魔化そうとする。しかし、彼は目を細めながらじぃ……と真田を凝視して動かない。やがて観念した真田は目を逸らし、わざとらしく肩を竦めた。
「……失恋、した……みたいな?」
「なんで疑問形なんだ」
「はは……まぁ、色々あって」
「お前みたいな男もフられるんだな」
「なんすかそれー」
あはは、と真田は笑い声をあげた。
実際ふったのは俺なんだけど、と心の中でつっこんでおく。
雷市の泣き顔が脳裏を過ぎった。
河川敷で一緒にバニラアイスを食べたこと。雷市に告白をされたこと。雷市の気持ちに応えられなかったこと。卒業式、泣きじゃくる雷市を抱きしめてやれなかったこと。あの日、桜が満開できれいだったこと。肩に寄せられた雷市の吐息や涙が、とても熱かったこと。
歳月が経つにつれて記憶は次第と薄れていくのに、その瞬間に感じた感情は今でも鮮明に、真田の胸の奥にくすぶっている。
――しつこいよな、俺も。
自嘲めいた笑みが、真田の口元に浮かぶ。
「そんならもう、野球のことで頭いっぱいにするしかねぇな」
気合い入れろと言わんばかりに、ばしっと強く尻を叩かれた。驚いて男を見ると、彼はにんまりと笑っている。真田たちの所属するチームは去年の都市対抗に大会に出場するも、二回戦目で敗退している。
今年こそ、このチームで日本一になりたい。熱い意志を宿した彼の目を見て、身の引き締まる思いがした。
「……はは! 俺にはもう野球しかないんで」
吹っ切れたように真田が笑う。
爽やかな、野球が好きで好きでたまらない野球小僧みたいな笑顔だった。
パァァン! と響いたキャッチャーミットの音は、先ほどよりもずっと力強く、ブルペンを震わせた。球が走っているのが、自分でもよくわかった。
←old / Next→