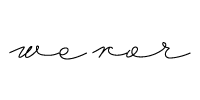今さら好きって言えるかよ (3)
桜が舞っている。
空は見事は快晴だった。
淡く色づいた桜ふぶきの中、雷市が必死に声を押し殺して泣いていた。
真田はそんな雷市の姿を目の当たりにして、なにも言えずに立ち尽くすことしかできない。
なにを言えばいいのか、わからなくなってしまった。
今日、真田は薬師高校を卒業する。
野球部の後輩たちから寄せ書きなんかもらったりして、涙もろい雷蔵が鼻を真っ赤にして泣くものだからさすがの真田もつられてちょっとだけ泣いて、そんな中でなぜか遠巻きに真田たち三年生を見つめる雷市に気がついた。
真田と目があった瞬間、雷市は逃げるように背を向ける。咄嗟にその後ろ姿を追いかけて、人気のない校舎裏でようやく雷市を捕まえた。
腕を掴んで引き留めると、振り向いた雷市はもうすでにぼろぼろと涙をこぼしていた。真っ赤に泣きはらした目に見つめられて、言葉につまる。
どうして、追いかけたりなんかしたんだろう。
雷市がまだ自分のことを好きなことは、わかっていたはずなのに。
本来なら気がつかないふりをして、一人で泣かせてやるべきだった。
それが雷市の告白を断った自分にできる、最善の行動だったんじゃないだろうか。
でも、身体が勝手に動いてしまっていたのだ。
雷市を放っておけなかった。
真田は神奈川にある社会人野球の企業チームへの入部が決まっている。
同じ関東とはいえ今までのように試合を見に行ったりはできないし、雷市と会う機会もほとんどなくなるはずだ。毎日のように顔をあわせて、一緒に野球をすることも、もうできない。
じわじわと、そんな実感がこみあげてくる。
「……雷市」
小さく、雷市の名前を呼んだ。
「っ……せん、ぱい」
弾かれたように真田を見上げた雷市が、顔をぐしゃぐしゃにして抱きついてくる。腰に回された両腕が小刻みに震えていた。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
「らいち」
「これで、最後に……する、から」
振り絞るように告げられた言葉に、どくん、と心臓が大きく跳ねた。
最後、という言葉がひどく重く胸にのしかかる
そう、最後なんだよ。
俺、卒業するし。
今までみたいに毎日会えるわけじゃないし。
会う理由だって、ないよな。
だって俺ら、ただの先輩と後輩だし。
ただの先輩と後輩のままであることを選んだのは自分のはずなのに、鼻の奥がつん、とする。
自分は、雷市とどうなりたかったのか。
結局、卒業まで答えはでなかった。
真田にとって雷市は特別な存在だった。
初めて出会ったあの日、雷市に打たれた規格外の場外ホームラン。
あれが真田の人生を百八十度すっかり変えてしまったと言っても過言ではない。
雷市と一緒に泥臭く本気になるのが楽しかった。
試合に勝って、汗だくになった雷市が「ナーダ最強!」と飛びついてきてくれるのが嬉しくてたまらなかった。
「お前んとこ打たせるの怖いわ」なんて軽口を叩いてこそいたけれど、本当はずっと頼もしく思っていた。
遠征帰りのバスの中で雷市が真田に寄りかかったまま爆睡し、ジャージが雷市の涎でべとべとになったのも、センバツではじめて甲子園に足を踏み入れたとき、雷市と顔を見合わせて笑いあったことも、試合に負けた次の日、悔しくて眠れないままいつもより早くグラウンドに向かったら同じように雷市がいて、なにも言わずに二人でキャッチボールをしたことも、ぜんぶぜんぶがいい思い出だ。
あっという間だった。
ずっとずっと、こんな毎日が続くような気がしていたけれど、終わりはあまりにも呆気なくやってくる。
「雷市」
びく、と雷市の身体が跳ねた。
「……お前のおかげで、俺……これからも野球続けるよ。ありがとな、雷市」
背中に回しかけた右腕を少しさまよわせて、そっと後頭部に添えた。
ぽんぽん、とあやすように頭を撫でると、「うー……」と雷市が小さく唸って、やがて嗚咽が聞こえてくる。
母親が丁寧にアイロンがけをしてくれたブレザーの背が、ぎゅうう、と強く握りこまれた。ひっく、ひっく、と泣きじゃくる雷市に、もう一度「ありがとう」と小さく繰り返す。
ざあ、と風が強く吹いて、桜の花びらがくるくると遠くへ泳いでいく。それを目で追いながら、真田は両目を眩しそうに細めた。
最後まで、雷市の気持ちに応えられなかった罪悪感のせいだろうか。
仰ぎ見た青空が眩しくて、目の奥がちかちかとした。
←old / Next→