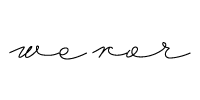今さら好きって言えるかよ
2022年8月に発行した雷真本のWeb再録です。
未来設定ねつ造あり
雷市:プロ野球選手
真田:社会人野球選手
小説+漫画で交互に話が進みます。
蝉が鳴いている。
じっとりとした暑さに、汗が首筋を伝う。
見上げた晴れ空は目眩がするほどに眩しく、真っ青で、まさに最高の野球日よりだ。
高くわきたった真っ白な雲を眺め、真田は静かに目を細めた。そして、通いなれたグラウンドへの道をゆっくりと歩く。
夏休み中ということもあり、校内はとても静かだ。毎日のように聞こえてきたブラスバンドの演奏も、もう聞こえない。
薬師高校野球部の――真田たち三年生の夏は、もう終わったのだ。
すべてを出し尽くした、と後輩たちの前で格好つけて笑ってはみせたが本当にまったく一切の悔いがなかったとは言えないし、正直なところ、真田このまま野球をやめるつもりでいた。
高校球児の中にはプロや大学、社会人チームで野球を続ける者もいるが、それは本当に限られたごく僅かな人間の話であって、真田は自分のことを「あっち側の人間」ではないと思っていたからだ。
父親が野球好きだったし、仲の良かった友達に誘われたし、他にやりたいこともなかったから、なんて理由で中学から野球をはじめて、これが結構なかなか楽しくて、多分だけど周りの人間より投手としての才能がちょっとあるんじゃないかと気づいて、真っ向勝負でバッターを捻じふせた瞬間がたまらなく気持ちよくって、試合で勝ったら母親が喜んでくれるのが嬉しくて、趣味のあわない父親がたまにキャッチボールに誘ってきたりして、それが特段楽しいわけではなかったけれど帰り道に父親がぽつぽつと話す野球選手の話に「ふうん」とてきとうに相づちを打ったりして、でも野球の名門校に行くような情熱はなく――そんなふうにほどほどに楽しんで野球と付きあってきたから、薬師高校野球部のゆるい空気感が真田にとってはちょうどよかった。
みんな真面目ではあったけれど、誰もが野球に本気ではなかった。
だから、真田たちの夏だって本来ならもっともっと早く終わっていただろうし、それこそ初戦で敗退していた可能性だってあったはずだ。それがどうだ。西東京大会の五回戦で、あの市大三高と本気の、魂と魂がぶつかりあうような熱い試合ができた。今までの薬師野球部だったら、あの血が沸きたつような興奮も、夜眠れなくなるような悔しさも、胸に穴が空いたような空しさも、全部味わえなかったものだと思う。
「……あいつに、会っちゃったんだもんなぁ」
ぽつりと独り言をもらした真田は、脳裏に一人の男の姿を思い浮かべて、小さく笑った。
――カキィン!
そんな矢先、鋭い音が学校内に大きく響き渡る。
真田ははっと顔を上げた。
青空を突き抜けて高く高く飛んでいくような鋭く、力強い快音。真田はこの音をよく知っていた。汗ばむような暑さの中で、ぶわりと全身に鳥肌が立った。気づけば真田はアスファルトを強く蹴り、グラウンドに向かって一直線に駆けていた。
フェンスに張りつくと、ガシャン、と網が音をたてて揺れる。真田は汗だくになりながら、食い入るようにグラウンドを見つめた。
そこには、バットを構える後ろ姿があった。
大きく踏みこみ、豪快にフルスイングをする。大きな笑い声とともに白球が遠くへ飛んでいく。
「……雷市」
真田は想わずその名前を口にしていた。
雷市だ。
雷市が、グラウンドに立っている。
真田の後輩である轟雷市は市大三高に破れたあと、離縁した母親の実家に預けられたのだと聞いた。
父親いわく「自分が真田たちの夏を終わらせてしまったんだと感じている」という話で、ずいぶんと落ちこんでいたようだった。
お前ってほんとばかだな、と言ってやりたかった。
真田も自分のことでいっぱいっぱいだったし、雷市が塞ぎこんでいたことにも気づいてやれなかった俺が一番ばかだとは思うけれど、雷市のせいで負けたなんて誰ひとり考えちゃいない。
野球ってそういうもんじゃねーだろ、と。
それから、俺たちがどれだけお前に感謝をしているか、お前とする野球が楽しかったか、お前のことを尊敬しているか。まったく伝わっていないだろう部員たちの想いを、あの後輩に教えてやりたくて、雷市がここに帰ってくるのをずっと待っていた。それはきっと真田だけじゃないはずだった。
編み目にかけた指先に、ぐっと力がこもる。
グラウンドが、野球そのものが、轟雷市を待ちわびていた。そう思えるほどにまばゆくて、胸が震えるような光景だった。
どれほど、その場に立ち尽くしていただろうか。
「また騒がしくなんぞ」
いつの間にか、傍らに雷蔵が立っていた。
真田は驚いて、その横顔を見つめる。
雷蔵は呆れたような、嬉しくってたまらないような目をしていて、真田もつられて笑った。再び視線をグラウンドに戻し、二人で雷市のバッティングを眺める。
「あいつ、帰ってきたんすね」
「うめーもんたらふく食ってきたってよ。そのくせ土産はてめーらの分しか買ってこねーし…」
「あはは、日頃の行いってやつですかね」
真田と雷蔵は目をあわせ、に、と笑いあった。
ばしっと乱暴に背中を叩かれる。
「こっからだぜ。お前も、あいつも」
「……はい。お世話になります」
かしこまった態度で頭を下げると、雷蔵は気まずそうに視線を泳がせたあと「そういうのいーから」ともう一度背中を軽く叩かれた。
三年生がほとんど来なくなったとはいえ、練習後の部室は相変わらず騒がしい。先に帰り支度を終えた真田は、三島や秋葉と話しこんでいる雷市に声をかけた。
「雷市、いつものやんの」
「うん」
雷市は当たり前のように頷いた。
それでこそ雷市だよな、と真田は嬉しくなって、別に隠し事にする必要もないのに雷市の耳元に手を添えながら顔を近づける。
「俺も行っていい?」
「……うん!」
雷市がぱあっと表情を輝かせる。
んじゃ後でな、と軽く雷市の肩を叩いて、後輩たちより先に学校を後にした。
――真田がああいうの可愛がるって意外だね。
そう言ったのはクラスメイトの女子だった。
偶然廊下で見かけた雷市を呼びとめ、とくに用事があったわけではないけれど、「次なんの授業?」「音楽……です」「へー雷市って歌うまい?」「う、うまくない……ので、苦手です」「雷市の歌聴いてみたいんだけど」だなんて会話をして、別れ際にポケットしまっておいた飴を押しつけた。その一連の光景を見て、彼女はそんな感想を述べたのだ。
そのとき、真田は「たしかに」と思った。
真田の友人たちとはまったくタイプが違うし、そもそも世話焼きなわけでも、面倒見がいい性格でもない。
思い返せば、こんなふうにちょっかいをかける後輩は雷市だけだった。真田はちょっと考えて「まぁ、話す機会多いからかな。あいつレギュラーだし」と笑って受け流した。
エースと四番打者、そしてどちらもクリンナップを担う主力メンバーともなれば、真田と雷市が会話する機会も自然と多くなる。
最初の頃こそ要領を得ない雷市との会話に「まぁ部活以外で話すこともねーしな……」なんて考えていた真田だったが、おどおどとした雷市の一挙一動がおもしろくて、つい構いたくなって、校内で見かけるたびに声をかけたりするうちに、一緒に帰るようにもなった。
やがて雷市が早朝と夜に河川敷で素振りをしていることを知り、軽い気持ちで「見にいってもいい?」と尋ねたのだ。
ただの興味本位だった。
朝から晩まで橋の下で素振りって昔のスポコン漫画みたいだなと思いながら、たしか差し入れにコンビニのおにぎりを買っていった気がする。具はなんだっただろうか。たぶん、ツナだった。あのとき「ツナうまいよな」という話をした記憶があるから。
あれから半年以上が経ったが、今でも真田はこうして雷市の自主練を見に行っている。
バットをがむしゃらに振る雷市の姿を見るのがなんでかとても好きで、暇さえあれば度々ここを訪れて雷市に(と、ときおり様子を見に来る父親にも)差し入れをするのが真田の日常にすらなっていた。
あっという間だったな、と思う。
真田の高校野球は、もう終わってしまった。
雷市と過ごした二年間はあまりにも濃密で、熱くて、だからこそ、いまだに胸の底でかすかな熱が燻っている。
まだ感傷に浸ってんのかよ、と苦笑いしながら、真田は橋の下に着いた。
多い茂った草むらから虫の声がする。日中よりはずっとマシだが、それでもじっとりと肌にまとわりつくような暑さが漂っていた。歩道に街灯があるとはいえ、薄暗い足下に気をつけながら階段を下りていく。真田の足音に気づいた雷市が、素振りをやめて振り返った。
「お疲れ」
左手に提げていたコンビニ袋を軽く持ち上げると、雷市の顔がパッと輝き、一目散に駆けよってくる。大好きなおやつを見つけた犬や猫みたいな反応に、真田は思わず笑った。
今夜の差し入れは、バニラのカップアイスだ。
雷市と階段に腰をおろして、スプーンとアイスを一緒に手渡す。
「うんめぇー!」
一口食べて、雷市は歓喜の声をあげた。
いくら人気のない河川敷とは言え、時間も時間だ。声でかいって、と咎めると、雷市は慌てて口を片手で押さえた。子どもみたいな反応に笑って、真田もアイスを口に運ぶ。
ひんやりとした優しい甘さが口いっぱいに広がって、すぐに溶けていく。もう一口食べた。ときどき吹く夜風が首筋や額を撫でていくのが心地いい。
隣を見やると、雷市は黙々とアイスを食べていた。がつがつと勢いよくがっつきそうなイメージに相反し、雷市はとても丁寧に一口一口をよく味わって食べる。轟家にとってはアイスは高級品なんだろうな、と思った。
「お前ほんとバニラ好きな。他に好きなアイスねぇの」
雷市はスプーンを咥えたまま瞬きをして、少し考えた。
「……食べねぇからわかんねぇ」
「そっか」
余計なことを聞いてしかったかもしれない。
しかし、雷市はたいして気にしていない様子でアイスをぱくっと頬張った。バニラアイスの味を確かめるように舌を動かして、うん、と深く頷く。
「でも俺、このアイス……ずっと一番好きだと思う」
真剣な横顔を見て、特別なんだといわれた気がした。
ちょっとだけどきっとしてしまって、誤魔化すように笑い声をあげた。
「それって、俺と一緒に食ったって思い出こみで? 雷市ってほんと俺のこと好きなー」
動揺して、また変なことを口走ってしまう。
でもこれぐらいのじゃれあいは男子高校生ならまぁよくあることだし、チームメイトに「愛してるぜー」なんて冗談も言ったりするし、別に変なことじゃないだろう多分きっと。そう、真田が自分に言い聞かせていると
「……うん」
雷市が小さく呟いて、顔を背けてしまった。
奇妙な沈黙が二人のあいだに生じる。
雷市はそっぽを向いたまま、なにも言わない。なぜだか真田は自分の頬がじわじわと熱くなっていくのを感じていた。
――あれ。
胸がざわざわとする。
「……先輩、俺」
ゆっくりと振り返った雷市の表情は、俯いていてよく見えない。それでも、強ばった声から雷市の緊張が伝わってくる。
まずくないか、これ。
そう直感した真田が口を開くが、もう遅かった。
「……真田先輩のことが、好き……です」
面を上げた雷市の瞳が、真田をまっすぐにとらえた。
熱くうるんだ両目が今にも泣き出しそうに歪んで、真田を見ている。
一瞬で、全身からぶわっと汗が吹き出した。
「……マジか」
左手で押さえた口から、上ずった声が漏れる。
雷市が、俺を好き?
それって先輩として尊敬してるってこと? だなんて茶化せるような空気ではなかった。明確にそういう対象として、雷市は真田に好意を寄せているのだとその目を見ればすぐにわかる。
「マ、マジ……です」
少しふやけたアイスのカップが、ぐっと雷市の手の中で歪む。
真田は雷市の顔をまじまじと見つめた。
雷市に対する不快感だとか嫌悪感はまったくない。
ただ、単純にびっくりしている。そもそも雷市が恋愛感情というか、雷市が野球以外に興味をもっていることに驚いた。しかも、その相手が自分だなんて。
――あの雷市が、俺のこと……え? いつから? 全然わかんなかったんだけど……こいつ、可愛いとこあるしなぁ。考えたことなかったけど、アリなのかも……。
試しに付きあってみてもいいかも、という考えが頭を過ぎった矢先、
「……真田先輩」
雷市の熱い眼差しに、はっとした。
雷市は本気で、真剣なんだ。
こんなにも純粋でひたむきに告白をしてきてくれている相手に対して、生半可な気持ちで応えちゃいけない。そう、思った。
自然と真田の背筋が伸びる。
雷市の目が街灯の明かりを反射して、静かな光をたたえていた。
きれいだな、と感じた。
雷市の目はいつだってまっすぐに、迷いなく、常に前を向いている。
真田はその目がとても好きだった。
雷市を見ていると、俺みたいな奴も本気になってもいいのかも、と思えた。
だからこそ真田はこの先も野球を続ける決心がついたのだ。雷市や雷蔵との出会いがなかったら、きっと今ごろ友人たちと「暇だわー」なんて笑いながらファミレスでだべっていたかもしれない。そんな夏休みもいいだろう。多分それなりに楽しいんだろう。それでも真田は、今の野球馬鹿になってしまった自分がいい。
自分を変えてくれた雷市に対しては、真摯でありたかった。
「……ごめん」
絞りだすように、切りだした。
雷市の表情が強ばった。
「俺も雷市のこと好きだし、マジで尊敬してるよ。けど、そういう対象としては見れねぇ……と思う」
慎重に言葉を選びながら告げたつもりだった。雷市を傷つけたいわけではなかった。
「ご、めんなさい……俺…」
雷市の声が震えていた。
「……なにも考えて、なくて……」
自分が想いを伝えたことによって真田との関係が変わってしまうこと、それが野球部に影響を及ぼす可能性があることに気がついたのだ。俯く雷市の肩は小刻みに震えている。気まずい空気に耐えかねた真田は
「あー! えっと、ほら! アイス! アイス溶けちまうから!」
わざと大声をあげてみせた。
雷市がぽかんとした顔で真田を見上げる。
「つーか、別に嫌とかじゃないし……むしろ嬉しいっていうか……これからも、お前と野球したいし! つうかするし! 卒業まで!」
ばしばしと肩を叩いて笑うと、雷市も「へへ……」とぎこちなく笑ってくれた。それから二人ですっかり溶けてしまったアイスをかきこんで、アイスで口周りをべっとりと汚した雷市に真田が声をあげて笑って、それから徐々に静かになった。けれど、先ほどまでの重苦しさはない。
川の向こうで光る街明かりを二人で眺めた。
「……真田、先輩」
雷市が、ふいに口を開く。
「これからも、一緒に……野球して……くれますか」
雷市の目が、少し不安そうに揺れている。
一緒の野球をしくれますか、だなんて、どこまでも雷市らしいお願いごとだった。真田はふ、と目を細めて雷市の頭をわしゃわしゃと撫でまわす。
「言ったじゃん。俺だって、まだお前と野球したいよ」
「っ……うん」
雷市の目から、ぼろっと涙がこぼれた。
その涙を拭おうと手を伸ばしかけて、やめた。それはやっちゃだめなことだと思った。
「……ありがとな、雷市」
代わりに何度も何度も、何度でも、雷市の背をあやすように優しく撫でた。
Next→